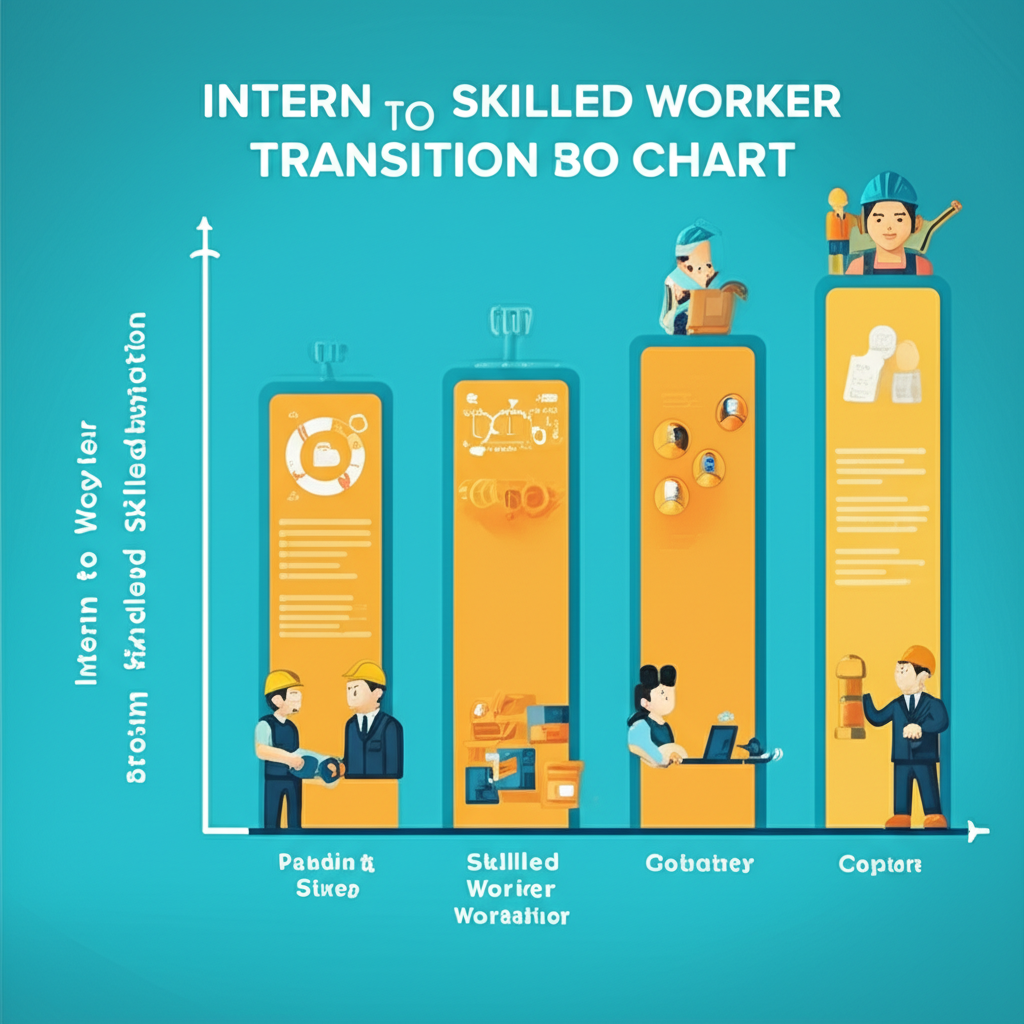
技能実習2号で頑張ってきた外国人の方が、特定技能1号という新しいステップへ進むことを考えている企業の人事ご担当者様にとって、どの仕事の経験が、どの新しい仕事の分野に繋がるのかを正確に知ることが、何よりも大切になります。
この記事では、技能実習2号と特定技能1号という二つの制度がどのように違うのか、そして、技能実習で経験した仕事の種類が、特定技能1号のどの分野の仕事に当てはまるのかを、具体的な対応関係がひと目でわかる比較表を交えて詳しく解説いたします。
- 技能実習2号と特定技能1号、それぞれの制度の目的と対象となる仕事の範囲
- 技能実習2号の経験が活かせる特定技能1号の具体的な仕事分野の組み合わせ
- 技能実習生がスムーズに特定技能へ移るために企業が注意すべき点と手続きの流れ
- 自社で受け入れている技能実習生の職種が、どの特定技能分野に移行可能かの見通し
目次
技能実習2号と特定技能1号制度の違いの理解、円滑な移行への鍵

外国人材の受け入れにおいて、技能実習制度と特定技能制度は重要な選択肢です。
特に、技能実習2号から特定技能1号への移行を考える際には、両制度の目的や内容の違いを正確に理解することが、円滑な手続きと外国人材の活躍を支援するための最初のステップとなります。
これらの制度は、日本で働くことを希望する外国人の方々や、彼らを受け入れる企業にとって、その仕組みや対象となる仕事の範囲が大きく関わってくるからです。
この章では、まず技能実習2号制度の概要と目的、続いて特定技能1号制度の概要と目的を解説します。
そして、両制度の具体的な相違点を明らかにすることで、外国人材の受け入れにおける正しい認識を深めます。
最後に、制度理解がもたらす円滑な手続きと活躍支援について述べ、これらの知識がどのように実務に役立つのかを示します。
| 比較項目 | 技能実習2号 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 国際貢献 (技術移転) | 国内の人手不足解消 |
| 在留期間 | 最長3年 (1号と合わせて。2号単独では通常2年) | 通算上限5年 |
| 技能水準 | 技能実習計画に基づく実習を通じて習得 | 試験等で確認された一定の専門性・技能 |
| 対象業務 | 約80職種150作業 (2024年4月時点、技能移転が目的) | 特定産業分野として定められた12分野 (2024年4月時点) |
| 転職の可否 | 原則不可 | 同一分野内または関連性の高い業務への転職は可能 |
これらの違いを把握することが、双方にとってより良い結果をもたらすための基礎となります。
技能実習2号制度の概要と目的
技能実習2号制度は、外国人の青壮年労働者が日本の企業などで働きながら技能や技術、知識を習得し、母国の経済発展に貢献することを目的とした在留資格です。
この制度は、日本が先進国として培ってきた技術やノウハウを開発途上国等へ移転するという国際貢献の一環として位置づけられています。
技能実習生は、技能実習1号(通常1年間)で基礎的な技能を習得した後、技能評価試験に合格することで技能実習2号へ移行します。
2号ではさらに専門的・実践的な技能を深めるための実習を原則として2年間行うことができます。
対象となる職種は、2024年4月時点で建設関係、食品製造関係、機械・金属関係など多岐にわたり、約80職種150作業に及びます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の趣旨 | 日本で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転による国際協力の推進 |
| 対象者 | 主に開発途上国の青壮年労働者 |
| 在留期間 | 通常2年間(技能実習1号と合わせると最長3年間) |
| 技能習得レベル | 習熟した技能 |
| 活動内容 | 雇用契約に基づき、技能実習計画に沿った技能等の習得活動 |
技能実習2号を良好に修了すると、一定の要件を満たせば特定技能1号へ移行する道も開かれています。
特定技能1号制度の概要と目的
特定技能1号制度は、国内の人材確保が困難な状況にある特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的として2019年4月に創設された在留資格です。
この制度は、深刻化する人手不足に対応し、日本経済・社会の持続可能性を維持するために導入されました。
特定技能1号の在留資格を得るためには、対象となる産業分野が実施する技能試験と日本語試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了することが必要です。
在留期間は通算で上限5年となっており、その間は受け入れ企業との雇用契約に基づいて就労します。
対象となる特定産業分野は、2024年4月時点で介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12分野です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の趣旨 | 中小・小規模事業者をはじめとした深刻な人手不足に対応するための即戦力確保 |
| 対象者 | 特定産業分野において相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する外国人 |
| 在留期間 | 通算で上限5年 |
| 技能水準 | 試験等で確認された、特定産業分野の業務区分において即戦力として活動できる水準 |
| 活動内容 | 受け入れ機関との雇用契約に基づき、特定産業分野の業務に従事 |
特定技能1号で働く外国人は、日本人と同等以上の報酬を受けることが保障されています。
両制度の相違点、外国人材受け入れにおける正しい認識
技能実習2号制度と特定技能1号制度は、外国人材が日本で働くための制度という共通点がありますが、その目的や内容は大きく異なります。
最も根本的な違いは、技能実習制度が「技術移転による国際貢献」を主目的とするのに対し、特定技能制度は「国内の人手不足解消」を主目的としている点です。
この目的の違いから、在留期間の上限、求められる技能水準、転職の可否、家族帯同の可否、受け入れ可能な職種・分野の範囲など、多くの点で具体的な制度設計が異なっています。
例えば、技能実習はあくまで「実習」であり、計画に沿った技能習得が求められるのに対し、特定技能は「労働力」として、即戦力となる専門性が求められます。
これらの違いを正しく認識することが、外国人材を受け入れる企業にとって、適切な制度選択と法令遵守につながります。
| 比較項目 | 技能実習2号 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 制度目的 | 国際貢献(技能等の母国への移転) | 国内の特定産業分野における人手不足の解消 |
| 在留期間(上限) | 最長3年(1号と合わせて。2号単独では通常2年) | 通算5年 |
| 求められる技能 | 技能実習計画に基づく習熟技能 | 特定産業分野における相当程度の知識・経験(試験等で証明) |
| 業務内容 | 技能実習計画に定められた実習作業 | 特定産業分野の業務全般(関連業務への従事も可) |
| 転職の可否 | 原則として不可(やむを得ない事情がある場合を除く) | 同一の業務区分内、または試験により技能水準の共通性が確認された業務区分間で可能 |
| 受入れ分野/職種 | 87職種159作業(2024年5月1日時点、今後変更の可能性あり) | 12分野(2024年4月時点、今後分野追加の可能性あり) |
| 家族帯同 | 不可 | 原則不可(特定技能2号へ移行すれば要件を満たせば可能) |
これらの相違点を理解せずに安易に制度を利用すると、意図しない法令違反や、外国人材とのミスマッチが生じる可能性があります。
制度理解がもたらす円滑な手続きと活躍支援
技能実習2号と特定技能1号という二つの制度の違いを正確に把握することは、外国人材の受け入れ手続きをスムーズに進め、彼らが日本で能力を十分に発揮して活躍するための基盤となります。
制度への理解が浅いと、申請書類の不備や、そもそも移行要件を満たしていないといった事態を招き、手続きが大幅に遅れたり、最悪の場合は不許可となったりする可能性があります。
逆に、それぞれの制度の目的、対象となる職種や分野、在留資格の要件などを深く理解していれば、移行の可否を早い段階で判断でき、必要な準備を効率的に進めることができます。
例えば、技能実習2号修了者が特定技能1号へ移行する際に試験が免除されるケースや、逆に試験が必要となるケースなどを事前に把握しておくことで、外国人本人への説明も的確に行え、無用な混乱を避けられます。
さらに、外国人材のキャリアプランや適性を考慮した上で、どちらの制度(あるいはどの分野)が本人にとって最適なのかを一緒に考えることが可能になり、定着率の向上やモチベーション維持にも繋がります。
| 制度理解によるメリット | 具体的内容 |
|---|---|
| 手続きの円滑化 | 申請書類の不備減少、審査期間短縮への寄与、移行パターンの的確な把握 |
| 外国人材の活躍支援 | 本人の希望やスキルに合った適切なキャリアパスの提示、ミスマッチの防止 |
| 企業側のリスク軽減 | 不適切な雇用による行政指導や罰則リスクの回避、安定的な人材確保プランの策定 |
| コミュニケーションの質の向上 | 外国人材への正確な情報提供による信頼関係構築、受け入れ後のサポート体制の充実 |
| 法令遵守(コンプライアンス) | 在留資格制度の正しい理解に基づく適正な外国人雇用の実現 |
企業の人事担当者様がこれらの制度について深い知識を持つことは、単に手続きをこなす以上の意味を持ちます。
それは、外国人材が日本で安心してその能力を発揮し、企業と共に成長していくための環境を整える上で、極めて重要な役割を果たすのです。
技能実習2号と特定技能1号の基本、目的と対象範囲の違い
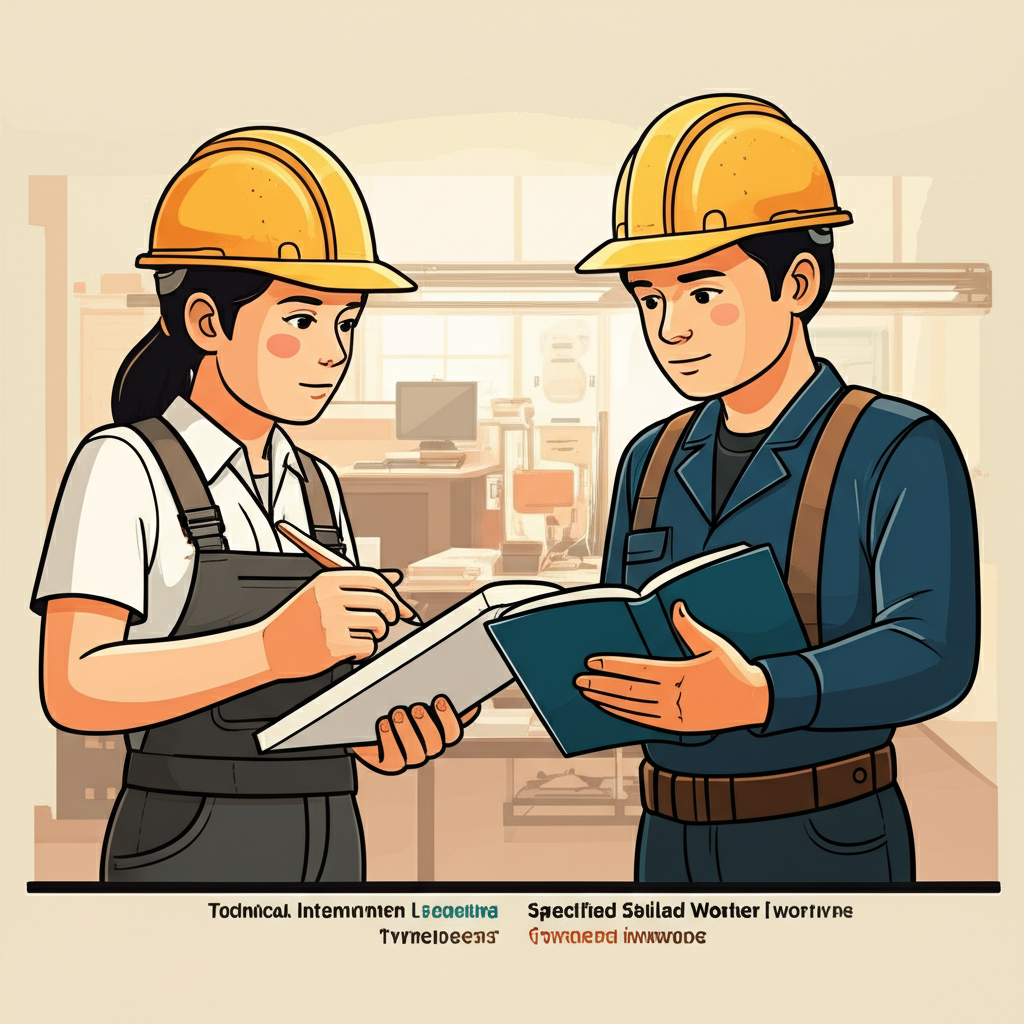
技能実習制度と特定技能制度は、外国人の方が日本で働くための重要な選択肢ですが、それぞれの制度の目的と対象となる仕事の範囲には明確な違いがあります。
この違いを正しく理解することが、技能実習生のスムーズな特定技能への移行や、企業が適切な外国人材を受け入れるための第一歩となります。
具体的には、「技能実習2号の目的と対象職種」「特定技能1号の目的と対象となる12分野」を把握し、両制度の「対象職種・分野の広がり」を比較し、常に「最新情報を公的情報源で確認する」ことが求められます。
これらの制度の違いを正確に把握することで、外国人材本人にとっても、受け入れ企業にとっても、より適切な選択と円滑な手続きが可能になります。
技能実習2号、その目的と対象職種
技能実習2号は、開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的とした在留資格です。
この制度では、外国人材が日本の企業等で働きながら実践的な技能・技術・知識を習得し、その成果が一定水準以上に達したと認められると、最長3年間の在留が可能です。
対象となる職種は、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係など、2024年5月時点で約90職種165作業に及びます。
| 主な対象職種(例) |
|---|
| 建設関係(とび、左官、鉄筋施工など) |
| 食品製造関係(パン製造、そう菜加工など) |
| 繊維・衣服関係(婦人子供服製造、寝具製作など) |
| 機械・金属関係(鋳造、溶接、金属プレス加工など) |
| 農業関係(耕種農業、畜産農業) |
| 漁業関係(かつお一本釣り漁業、養殖業など) |
| その他(介護、自動車整備など一部職種) |
注: 職種・作業は変更される場合があるため、最新情報は外国人技能実習機構のウェブサイト等で確認が必要
技能実習2号を良好に修了すると、特定技能1号への移行において一部試験が免除されるなど、キャリアアップの道が開かれることがあります。
特定技能1号、その目的と対象となる12分野
特定技能1号は、国内人材の確保が困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることを目的とした在留資格です。
この制度は、深刻な人手不足に対応するため2019年4月に創設され、対象となるのは12の特定産業分野です。
特定技能1号の在留期間は通算で最長5年間となります。
| 特定産業分野 |
|---|
| 介護 |
| ビルクリーニング |
| 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 |
| 建設 |
| 造船・舶用工業 |
| 自動車整備 |
| 航空 |
| 宿泊 |
| 農業 |
| 漁業 |
| 飲食料品製造業 |
| 外食業 |
*注: 分野は今後見直される可能性あり。
最新情報は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認が必要*
特定技能1号で働くためには、原則として各分野が定める技能試験と日本語試験に合格する必要がありますが、技能実習2号を良好に修了した場合はこれらの試験が免除されるケースが見られます。
対象職種・分野の広がり、技能実習と特定技能の比較
技能実習制度と特定技能制度では、対象となる仕事の範囲、つまり職種や分野の数とその内容に大きな違いが見られます。
技能実習2号が約90職種165作業と非常に多岐にわたるのに対し、特定技能1号は人手不足が深刻な12分野に限定されています。
この違いは、それぞれの制度の目的、すなわち技能実習が「技能移転による国際協力」、特定技能が「国内の人手不足解消」を主眼としている点から生じています。
| 項目 | 技能実習2号 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 目的 | 技能等の移転による国際協力 | 国内の人手不足解消 |
| 対象範囲 | 約90職種165作業(幅広い産業分野) | 12の特定産業分野(人手不足が深刻な分野に限定) |
| 在留期間(目安) | 最長3年(1号と合わせて) | 通算最長5年 |
| 技能水準 | 実習を通じて習得 | 即戦力となる専門性・技能 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 不可 |
| 転職の可否 | 原則として同一企業、同一職種での実習の継続 | 同一分野内または技能水準が共通と認められる分野間で可能 |
このように、対象となる仕事の範囲や制度の趣旨が異なるため、技能実習2号修了者が特定技能1号へ移行する際には、自身が経験した職種と移行を希望する分野の関連性が重要になります。
最新の対象職種と分野、確認すべき公的情報源である出入国在留管理庁や外国人技能実習機構
技能実習の対象職種や特定技能の対象分野は、社会経済情勢の変化や産業界のニーズに応じて見直されることがあります。
そのため、常に最新かつ正確な情報を入手することが不可欠です。
具体的には、出入国在留管理庁のウェブサイトでは特定技能制度に関する最新情報や告示、関連資料が公開されており、外国人技能実習機構(OTIT)のウェブサイトでは技能実習の対象職種・作業の一覧や制度概要が提供されています。
これらの公的機関の情報は、最も信頼性が高い情報源と言えます。
| 公的情報源 | 主な確認可能情報 |
|---|---|
| 出入国在留管理庁 | 特定技能制度の概要、対象分野、告示、Q&A、統計情報 |
| 外国人技能実習機構 (OTIT) | 技能実習制度の概要、対象職種・作業一覧、各種様式 |
| 厚生労働省 | 特定技能制度(一部の分野)、技能実習制度に関する情報 |
| 各特定産業分野の所管省庁 | 各分野の運用要領、試験情報など |
制度改正は随時行われるため、これらのウェブサイトを定期的に確認し、常に最新の情報を基に手続きや判断を行うように心がけましょう。
技能実習2号から特定技能1号への移行、職種と分野の関連性
移行可否の基本原則、技能実習での経験と特定技能分野の業務内容
技能実習2号の職種と特定技能1号の分野、その対応関係を示す比較表
移行しやすい職種・分野の具体例、建設・農業・飲食料品製造業
溶接職種から素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野への移行パターン
移行時の注意点、職種・分野の関連性が不明確なケース
特定技能評価試験の免除、技能実習2号の良好な修了実績
円滑な移行手続き、人事担当者が押さえるべきポイント
技能実習生が特定技能へスムーズに移行するためには、人事担当者による事前の準備と適切な情報共有が極めて重要になります。
これからご説明する技能実習計画の確認から外国人材本人との意思疎通に至るまで、各ステップを確実に実行することが、手続きの遅延を防ぎ、双方にとって望ましい結果に繋がります。
これらのポイントを押さえることで、外国人材の受け入れを成功させ、企業の持続的な発展に貢献する体制を構築できます。
技能実習計画と評価調書の重要性、移行審査における役割
技能実習生の特定技能への移行手続きにおいて、「技能実習計画」と「評価調書」は、外国人材が適正に技能実習を修了したことを証明するために不可欠な書類です。
技能実習計画には、実習の目標、内容、期間などが詳細に記載され、評価調書は実習生の技能習熟度や勤務態度を客観的に評価した記録となります。
これらは、出入国在留管理庁による移行審査の際に、技能実習2号の良好な修了を判断する根拠資料として扱われます。
| 書類名 | 主な内容 | 審査における役割 |
|---|---|---|
| 技能実習計画 | 実習目標、実習内容、期間、指導体制 | 計画通りの実習が行われたかの確認 |
| 技能実習日誌 | 日々の実習内容、指導内容、実習生の所見など | 実習の具体的な実施状況の証明 |
| 評価調書(旧技能実習評価試験の結果等) | 技能習熟度、勤務態度、日本語能力などの評価 | 技能実習2号の修了レベルに達しているかの判断材料 |
これらの書類を日頃から適切に作成し、保管しておくことが、移行手続きを円滑に進めるための第一歩です。
社内共有用、移行対象職種と分野の関連性リスト作成とその活用
技能実習2号の職種と特定技能1号の分野の関連性をまとめた「移行対象職種と分野の関連性リスト」を作成し、社内で共有することは、外国人材受け入れに関する共通認識の醸成に繋がります。
特に複数の部門が関わる場合や、今後も継続して外国人材の受け入れを検討している企業にとっては、非常に有効です。
このリストがあることで、例えば、製造現場の責任者と人事担当者が、ある技能実習生がどの特定技能分野へ移行できる可能性があるのかを迅速かつ正確に把握できるようになります。
| 記載項目例 | 内容 | 活用例 |
|---|---|---|
| 技能実習の職種・作業名 | 例:溶接(手溶接、半自動溶接) | 対象となる実習生のスキルを特定 |
| 対応する特定技能の分野・業務区分 | 例:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(溶接) | 移行先の候補を明確化 |
| 試験免除の可否 | 技能実習の職種・作業と特定技能の分野・業務区分の関連性に基づく | 特定技能評価試験の受験要否を判断 |
| 社内担当部署 | 人事部、製造部など | 関係部署間の連携を促進 |
| 備考 | 移行時の注意点、必要な社内手続きなど | 個別ケースへの対応を円滑化 |
このリストは、出入国在留管理庁や厚生労働省が公表している最新情報を基に作成し、定期的な見直しを行うことで、常に正確な情報に基づいた判断が可能となります。
必要な試験と提出書類の事前準備、リストアップの推奨
特定技能1号へ移行するためには、原則として「特定技能評価試験」と「日本語能力試験」に合格する必要がありますが、技能実習2号を良好に修了した場合はこれらの試験が免除される場合があります。
試験免除の対象となるかどうかを早期に確認することが重要です。
免除されない場合は、試験の申込時期や実施頻度を把握し、計画的に準備を進めなければなりません。
また、移行申請には、在留資格変更許可申請書、雇用条件書、特定技能外国人の支援に関する計画書など、平均して10種類以上の書類が必要となります。
以下は、代表的な提出書類の一部です。
| 書類の種類 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 外国人材本人の情報、変更後の在留資格に関する情報 |
| 特定技能雇用契約書の写し | 雇用条件、業務内容、報酬額などを明記したもの |
| 雇用条件書の写し | 労働基準法等に基づき、労働条件を明示したもの |
| 技能実習2号修了を証明する資料 | 技能実習計画満了証明書、技能検定3級等の合格証の写しなど |
| 特定技能外国人の支援計画書 | 生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供など、支援内容を記載 |
| 手数料納付書 | 収入印紙を貼付 |
これらの試験や書類を事前にリストアップし、準備のスケジュールを立てておくことで、申請手続きの遅延を防ぎ、スムーズな移行を実現します。
登録支援機関の活用検討、専門的サポートによる負担軽減
「登録支援機関」とは、特定技能外国人の受け入れ企業に代わって、または企業と共同で、外国人材が日本で安定的かつ円滑に活動できるよう、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を行う機関です。
特に中小企業で人事担当者の業務範囲が広い場合や、初めて外国人材を受け入れる場合には、その専門的なサポートが大きな助けとなります。
登録支援機関は、煩雑な申請書類の作成サポートから、住居の確保、日本語学習の機会提供、日本人との交流促進まで、10項目にわたる法定の支援業務を提供します。
| 登録支援機関選定のポイント | 確認事項 |
|---|---|
| 支援実績と専門性 | これまでの特定技能外国人の支援実績、得意とする業種や国籍など |
| 支援内容の具体性 | 法律で定められた支援以外に、独自のサポートがあるか、企業や外国人のニーズに対応可能か |
| コミュニケーション体制 | 報告・連絡・相談の頻度や方法、担当者との相性 |
| 費用 | 支援委託料の内訳、追加費用の有無など |
| 対応言語 | 外国人材の母国語に対応できるスタッフがいるか |
自社のリソースや外国人材の状況を考慮し、信頼できる登録支援機関を選定することで、企業側の負担を大幅に軽減し、法令遵守を確保しながら外国人材の受け入れを進めることができます。
外国人材本人との丁寧な意思疎通、キャリア希望の尊重
技能実習から特定技能への移行は、外国人材本人にとって日本でのキャリアにおける重要な転換点となります。
そのため、企業側は移行手続きを進める前に、外国人材本人と少なくとも1回以上は個別の面談の機会を設け、丁寧な意思疎通を図ることが不可欠です。
面談では、特定技能制度への理解を深めてもらうとともに、本人のキャリアに関する希望、例えば「どのような業務に挑戦したいか」「将来的にどのようなスキルを身につけたいか」などを具体的にヒアリングします。
意思疎通の際に確認すべき項目の例は以下の通りです。
| 確認項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 特定技能制度への理解度 | 制度の目的、在留期間、業務内容などについて、本人が正しく理解しているか |
| 移行後の業務内容への希望と適性 | 本人が希望する業務と、企業が任せたい業務、そして本人のスキルとのマッチング |
| 日本での生活やキャリアの目標 | 5年後、10年後の目標、日本で学びたいこと、将来母国で活かしたい経験など |
| 移行手続きや生活に関する不安 | 家族のこと、住居のこと、言語の壁など、抱えている不安や疑問がないか |
| 健康状態や労働に関する意思確認 | 健康状態に問題がないか、特定技能として働く意思が明確にあるか |
外国人材のキャリア希望を尊重し、可能な限り本人の意向に沿った形で移行後の業務内容を決定することが、モチベーションの向上と長期的な定着に繋がります。
これにより、企業と外国人材双方にとってより良い関係を築くことができます。
外国人材活躍への道、最新情報確認と専門家活用の重要性
外国人材が日本で持てる力を最大限に発揮し、企業と共に成長していくためには、絶えず変化する制度の最新情報を正確に把握し、必要に応じて専門家の知恵を借りることが不可欠です。
具体的には、公的情報の継続的な確認、専門家への相談による複雑なケースへの対応、そして企業が担うべき共生社会実現への役割を理解し、技能実習と特定技能の両制度を戦略的に活用する視点が求められます。
これらのポイントを押さえることで、外国人材の受け入れと活躍支援を円滑に進め、企業と外国人材双方にとってより良い結果をもたらします。
制度変更への対応、最新の公的情報の継続的な確認
外国人材の受け入れに関する制度や要件は、社会情勢の変化に合わせて見直されることがあります。
そのため、出入国在留管理庁や厚生労働省、外国人技能実習機構(OTIT)などが発信する最新の公的情報を定期的に確認することが、法令遵守の観点からも極めて重要になります。
例えば、技能実習制度や特定技能制度の対象職種・分野の変更、申請書類の様式改訂、新たな通達などは、これらの省庁のウェブサイトで少なくとも月に一度は確認する習慣をつけることが望ましいです。
| 情報源の名称 | 確認すべき主な情報 |
|---|---|
| 出入国在留管理庁 | 在留資格制度全般、特定技能制度の最新情報、Q&A |
| 厚生労働省 | 技能実習制度、特定技能外国人の雇用管理指針、関連通知 |
| 外国人技能実習機構(OTIT) | 技能実習計画の認定、技能実習生保護に関する情報、統計資料 |
これらの情報を常にアップデートしておくことで、予期せぬトラブルを未然に防ぎ、スムーズな受け入れ手続きを実現できます。
専門家である登録支援機関や行政書士等への相談、複雑なケースでの対応
登録支援機関は、特定技能外国人材の受け入れ企業に代わって、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施などを行う機関であり、行政書士は、出入国管理に関する申請書類の作成や手続き代行を専門とする国家資格者です。
特に、初めて外国人材を受け入れる場合や、過去に申請で苦労した経験がある企業、あるいは技能実習から特定技能への移行で職種・分野の関連性が不明確なケースなど、自社だけで判断が難しい場合には、これら専門家のサポートを受けることで、手続きにかかる時間や労力を大幅に削減できるでしょう。
例えば、年間数十件以上の外国人材関連の申請実績がある専門家を選ぶことも一つの目安です。
| 相談先の専門家 | 主なサポート内容 | 相談するメリット |
|---|---|---|
| 登録支援機関 | 特定技能支援計画の作成・実施、定期的な面談、生活オリエンテーション | 外国人材の職場定着支援、法令遵守のサポート |
| 行政書士 | 在留資格認定・変更申請書類の作成、申請取次、入管との折衝 | 複雑な申請手続きの代行、許可の確実性向上 |
専門家の知見を活用することで、企業は本来の事業活動に集中しつつ、外国人材の適正な受け入れと活躍支援を実現することが可能です。
外国人材との共生社会実現に向けた企業の役割
外国人材が日本社会の一員として安心して生活し、その能力を十分に発揮できる環境を整えることは、受け入れ企業にとって重要な社会的責任であり、持続的な企業成長にもつながります。
例えば、日本語学習の機会提供、文化や習慣の違いを理解するための研修の実施、地域社会との交流イベントへの参加促進など、企業ができることは多岐にわたります。
社内に相談窓口を設置し、少なくとも2ヶ国語以上で対応できる体制を整えることも有効な手段です。
| 取り組みのカテゴリ | 具体的な施策例 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| コミュニケーション支援 | 日本語学習機会の提供、多言語対応ツールの導入、社内通訳者の配置 | 意思疎通の円滑化、業務効率の向上 |
| 生活支援 | 住居探しのサポート、銀行口座開設・携帯電話契約の支援、日本の生活習慣教育 | 生活基盤の安定、早期の日本生活への適応 |
| 文化・習慣への配慮 | 宗教的配慮(祈祷スペースの確保等)、異文化理解研修の実施、母国文化紹介イベント | 相互理解の促進、ハラスメント防止、職場環境の向上 |
| キャリア形成支援 | 資格取得支援、社内研修制度への参加奨励、キャリア相談窓口の設置 | モチベーション向上、長期的な定着、企業への貢献意欲の醸成 |
こうした取り組みを通じて、外国人材が働きがいを感じ、能力を最大限に発揮できる環境を構築することが、真の共生社会実現への第一歩となるのです。
技能実習と特定技能、両制度を活用した人材戦略
技能実習制度と特定技能制度は、それぞれ目的や特徴が異なりますが、これらを戦略的に組み合わせることで、企業はより柔軟かつ計画的に外国人材を確保し、育成することが可能になります。
例えば、まずは技能実習生として3年間受け入れて技術と日本語能力の基礎を育成し、その後、本人の希望と適性に応じて特定技能1号へ移行させることで、最長で合計8年間(技能実習3年+特定技能5年)の就労が可能となり、中長期的な人材育成と戦力化を図ることができます。
特に製造業や建設業など、一定の熟練期間を要する職種では有効な戦略と言えるでしょう。
| 項目 | メリット | 留意点 |
|---|---|---|
| 人材確保の柔軟性 | 技能実習からのステップアップによる安定的な人材確保、特定技能からの直接雇用も可能 | 各制度の目的・要件の理解、移行時の手続き・条件の確認が必要 |
| 人材育成の連続性 | 技能実習での基礎教育から特定技能での専門性向上へと連続的なキャリアパスを提供 | 移行対象職種・分野の関連性、本人のキャリア希望との整合性が重要 |
| 長期的な戦力化 | 最大8年間(技能実習3年+特定技能5年)の雇用が可能 | 在留資格の更新手続き、特定技能2号への移行可能性も視野に入れたキャリアプランニング |
| 受入コスト | 技能実習期間中の監理費、特定技能移行時の支援コストなどを総合的に考慮 | 各制度で必要な費用が異なるため、トータルコストでの比較検討が必要 |
各制度の特性を深く理解し、自社の事業計画や人材ニーズに合わせて最適な組み合わせを検討することが、外国人材活用の成功に繋がります。
よくある質問(FAQ)
技能実習2号と特定技能1号では、外国人労働者の給与・待遇にどのような違いがありますか?
特定技能1号では、受け入れ企業は外国人労働者に対し、同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を支払うことが義務付けられています。
一方、技能実習2号では、最低賃金法などの労働関係法令が適用されますが、必ずしも日本人と同等以上の報酬が保証されるわけではありません。
これが大きな違いです。
技能実習2号を修了した後、特定技能1号へ移行する際、別の会社で働くことはできますか?
はい、可能です。
技能実習2号を修了した方が特定技能1号へ移行する際、必ずしも実習先だった企業で継続して働く必要はありません。
移行先の特定技能1号の分野が技能実習での職務内容と関連しており、新たな受け入れ企業が見つかれば、その企業と雇用契約を結び働くことができます。
技能実習2号を「良好に修了」とは、具体的にどういうことですか。また、特定技能評価試験は免除されますか?
技能実習2号を「良好に修了」とは、一般的に技能実習計画を適切に終え、技能検定3級(またはこれに相当する技能実習評価試験)に合格している状態を指します。
この条件を満たし、かつ技能実習の職種と移行を希望する特定技能1号の分野に関連性が認められる場合、技能試験と日本語試験の一部または全部が免除されます。
技能実習での職種と、希望する特定技能1号の分野が直接関連しない場合、移行は無理でしょうか?
いいえ、諦める必要はありません。
技能実習で経験した職種と特定技能1号の分野に直接的な関連性が低い場合でも、希望する特定技能分野の技能試験と日本語試験に合格すれば、特定技能1号へ移行することが可能です。
技能実習2号を修了していることで、日本語試験が免除されるケースもありますので、最新の情報を確認してください。
企業が技能実習生から特定技能への移行手続きを進める際、特に気をつけるべき点は何ですか?
まず、技能実習2号の対象職種と、移行先の特定技能1号の分野との間に関連性が求められるという移行条件を正確に理解することが重要です。
加えて、外国人本人の明確な移行意思の確認、必要な申請書類の準備と内容の精査、そして在留資格変更許可申請を適切なタイミングで行うことが求められます。
移行手続きは複雑ですので、早めに専門家や登録支援機関に相談しましょう。
特定技能外国人を受け入れる企業は、必ず登録支援機関にサポートを依頼する必要がありますか?
いいえ、必ずしも登録支援機関に委託する必要はありません。
受け入れ企業が、出入国在留管理庁の定める支援基準(生活オリエンテーションの実施、住居確保の支援、日本語学習機会の提供など)をすべて満たせる体制を自社で構築できる場合は、「自社支援」として行うことが可能です。
ただし、これらの要件をクリアするのが難しい場合は、登録支援機関に支援業務の全部または一部を委託するのが一般的です。
まとめ
この記事では、技能実習2号で経験を積まれた外国人の方が特定技能1号へ移行する際に、最も重要な「技能実習の職種」と「特定技能の分野」がどのように結びつくのかを、具体的な比較表を使いながら詳しくご説明しました。
この記事のポイントは以下の通りです。
- 技能実習2号と特定技能1号の制度目的、対象となる仕事の範囲の違い
- 技能実習の経験(例えば溶接)が特定技能のどの分野(例えば素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)に活かせるかの具体的な対応関係
- スムーズな移行手続きを進めるための、企業側での書類準備や外国人ご本人との話し合いの重要性
- 常に最新の公的情報を確認し、必要に応じて登録支援機関などの専門家の力を借りること
技能実習生の特定技能への移行をご検討中の人事ご担当者様は、まずこの記事で解説した職種と分野の関連性を把握し、社内での準備や外国人ご本人との確認作業を進めていくことが大切です。


